

作家を目指していたわけでもなければ、文学青年でもなかった。青春時代に影響を受けたのは、もっと別のことでした
埼玉在住ながら東京の中学校への遠距離通学。片道1時間以上の時間を持て余した磯﨑氏はある本を手に取る。北杜夫の『船乗りクプクプの冒険』だ。
この小説に衝撃を受け、北杜夫作品を全て読むことになる。文学青年への道へ一直線…と思いきや、別の新しい出逢いがあった。音楽、ロックである。
高校時代は音楽一色。聞くのも好きだったし、自分で演奏もしていました。大学時代は体育会のボート部に入っていたし、小説とは接点のない生活を送っていました
その後、「世界を見てみたい」という理由で商社を選び、会社員へ。
入社10年目に海外駐在の話がきた。駐在先は、アメリカのミシガン州デトロイトだった。

当時のデトロイトは、全米一治安の悪い街という印象で。でも実際は森と湖に囲まれたとても住み心地の良い街でした。取引相手はゼネラル・モーターズ(GM)、フォード、クライスラー、いわゆるビッグ・スリーと呼ばれるアメリカの三大自動車メーカー。日本で10年の営業経験があるとは言え、30歳そこそこの若造と仕事をしてくれるのか内心ビクビクしていました。そんな心配をよそに、相手の社長や副社長はあっさり会ってくれたんです。
アメリカは移民が集まって作られた国だから、人種や年齢で差別することは許されないことなんです。アメリカの小学校に通い始めた長女が最初に習ったことは『Fairness(公平さ)』について。アメリカでは幼い頃からそれを徹底的に教え込まれるんです。
―ビジネスの場でもそれを感じたのですね。
”若いから”とか”日本人だから”といった理由で相手にされないという事はありませんでした。でも、過去に取引をした実績があるから優遇されるという事もない。純粋な競争だから厳しい面もありました。でも、自分にはその方が働きやすかったんだよね。
日本は肩書や会社の格で相手を見定めるようなところがあるし、仕事の本題に入るまでに様々な障害をクリアしなければならない。アメリカで働いて、日本がいかにヒエラルキーに縛られた物の見方をしているかということに気づきました。人間関係のしがらみ、商談に入る前の事前説明、そういった労力が当たり前になっていることに、日本にいる頃は気づかなかった。でもアメリカでは前置き無しで本題にすぐ入れたから、僕にとってはずっと働きやすかったんです。

会社員として着実に歩みを進める磯﨑氏に執筆活動の機会が訪れる。それは磯﨑氏にとって転機ではなく、ある経験の延長線上にある外界との接し方の一つだった。
磯﨑氏は、渡米以前に手に取った芥川賞受賞作品『この人の閾(保坂和志※1 著)』で『船乗りクプクプの冒険』以来の感覚を得る。作家 保坂和志氏との出会いが、小説を書くきっかけとなったのだ。
保坂さんのホームページの掲示板で保坂さんファンとやりとりしていて、僕が一時帰国するタイミングで保坂さんご本人と、ファン何人かで集まることになったんです。いわゆるオフ会ですね。本物の小説家と会うなんて初めてだから凄く緊張したけど、いたって気さくな人で楽しい時間を過ごしました。文学談義なんかしなくて、夜通しカラオケで歌ってた(笑)
保坂さんから『あなたは面白い。海外で面白い経験もしてるだろうから、何か書いてみて』と言われました。そこで、短いエッセーを書いたら、『面白いからすぐに小説にしなきゃだめだ!』と言われるがまま、原稿用紙100枚くらいの小説に書き直したんです。『面白い。でも、これではデビューできない』と言われた。すると僕もちゃんと書かないといけないという気がしてきて、帰国後に全く違う小説に書き直して、保坂さんに認められるためにも保坂さんが選考委員をしている文藝賞※2に応募したんです。
磯﨑氏は2007年『肝心の子供』で第44回文藝賞を受賞してデビュー。2009年には『終の住処』で第141回芥川賞を受賞した。
その間も、磯﨑氏は転身せず会社員を続けている。一体どのような心境だったのだろうか。磯﨑氏の創作活動における価値観の背景には、子の誕生があった。
正直に言うと、昔は子どもが好きじゃなかったんです。若くして結婚して身を固めた同期が気の毒に思えたほどでした。でも、実際自分の子どもが産まれると、かつての自分が恥ずかしくなるくらい子どもがかわいかった。子どものためなら自分の命を喜んで差し出せる、それくらい価値観が180度変わった出来事だったんです。
※1 保坂 和志(ほさか かずし)
1956年、山梨県生まれ。鎌倉で育つ。早稲田大学政経学部卒業。1990年『プレーンソング』でデビュー。1993年『草の上の朝食』で野間文芸新人賞、1995年『この人の閾(いき)』で芥川賞、1997年『季節の記憶』で平林たい子文学賞、谷崎潤一郎賞、2013年『未明の闘争』で野間文芸賞、2018年、『ハレルヤ』所収の『こことよそ』で川端康成文学賞を受賞。その他の著作に『カンバセイション・ピース』『小説の自由』『あさつゆ通信』『猫の散歩道』ほか。
※2 文藝賞
文藝賞は、1962年に創設された文学賞で、小説ジャンルにおける「新人の登竜門」と位置づけられている。過去の受賞作に『なんとなく、クリスタル』(田中康夫 著)、『インストール』(綿谷りさ 著)等がある。

人間は健全に老いていくと自分のためではなく、他者のために生きるようになるんだと思いました
結局、人間は健全に老いていくと自分のためではなく、他者のために生きるようになるんだと思いました。僕の場合はその他者が子どもだったけど、血縁関係に関係なく自分よりも大切な存在が、自分の外側に存在するということに気付いて、自己実現ではなく外界に奉仕するような生き方に変わっていくのではないか。僕にとって小説を書くことは、そういった考えの実践でした。
―2つの職業を持つことに苦労されましたか?
サラリーマンという守られた世界から突然小説という野蛮な世界でスポットライトをあびるようになって不安だったけど、会社の人たちは僕のデビューをすごく喜んでくれました。自分自身もっと会社員の顔と小説家の顔を使い分けたり、股裂きのように苦しむかと思ったら、全然そんなことはない。むしろ統合されていく感覚がありました。
―“統合”というのは?
会社員として言っていることも小説で書いていることも、結局同じことを言っているなと。サラリーマンをしながら作家をしていたから分かったことですが、自分が大事にする価値観というかコア(核)な部分は、簡単に使い分けたりできるものではないんです。採用に携わっていた関係上、人生観とか生きる意味とか、そういう人間のコアな部分を話す仕事だったというのもあったかもしれません。僕にとって一番大事なのは自己実現ではなくて、外の世界にどう奉仕するかということ。小説家としてもそうだけど、会社員としてもそうなんです。個人の出世なんかより、会社の存続の方が大事ですからね。
―会社員時代、印象に残った人はいますか?
人事や広報に携わっていた頃、当時の社長(槍田 松瑩代表取締役社長)と仕事を一緒にする機会がよくありました。大きな会社なので営業時代は社長に会う機会などなかったので、社長というはもっと怖い人なのかと思っていたのですが、実際お会いすると、まったく権威的なところのない、組織の将来にとってなにが最善かを常に考えているような方でした。
会社って、外から見ると会社自体がひとつの人格を持っていて、全員が同じ考えをしているように思えるけど、実際は同じ会社でも全然違う考えを持った人が沢山いますよね。いろんな意見が出る中で、最善の策、最善の意思決定を真剣に考えているものが経営なんだと思います。『長いものには巻かれよ』というような人もいる中で、組織が間違っている方向へ進もうとしているときに、軌道修正できる人がいる組織というのが、健全な組織なのだと思います。

面接は暗記能力を披露する場ではない
採用で学生を身近で見てきた経験上、個性を埋没させるリクルートスーツや、あらかじめ用意された答えほど意味がないと磯﨑氏は語る。
人材開発室の室長だったとき、年間500人以上の人を面接しました。いつも感じていたのは、就活中の学生がリクルートスーツを制服のように着ていることの異常さ。本当にあれ(リクルートスーツ)は何の意味もないと思う。
以前、海外大の学生を採用するためにロンドンやアメリカ、北京で採用面接を行いましたが、彼らは実際に社会で働くときに着る服装で面接に来ます。海外大の学生は、なぜ日本人はみんな同じ恰好ばっかりなんだと不思議がっていました。
極端な話、恰好なんてどうでもいいんだよね。もちろん、相手に不快な印象を与えるのは良くないけど。あらかじめ用意された志望動機も、さして参考にならない。今の採用面接の多くは、エントリーシートを暗記して喋る能力を問うてるみたいだもんね。
面接官は何を見ているか?話す力が働く姿をイメージさせる
実際、面接時間の20分か30分で分かることなんて、たかが知れてる。書類を読んだら分かる事を一方的に語られるよりも、一緒に窓の外を見て『あの建物、何だろうね』みたいな話題を、リラックスして話したりする時間の方がよっぽど意味がある。会話ができて、“場”を成立させられる人というのは、実社会でもやっていける可能性を感じさせてくれます。そういう子は、得意先を訪問しても、ちゃんと話ができるだろうから。
「周囲の評価」よりも「自分らしさ」を
就活は縁と運に依る所も大きいと思います。そもそも企業が学生を選ぶというスタンスがおかしい。学生が自分の人生を決める機会なんだから、憲法の職業選択の自由にもあるように、最終的な決定権は学生にあるんです。学生も、企業に気に入られるというよりも、自分が一番自分らしく活躍できる場はどこなのか。そこを考えてほしいですね。
今の若い人は、減点思考で失敗することに対しての恐れが強い。評価に敏感過ぎる気がする。状況によって求められている役割なんかを瞬時に察知して、上手に立ち回れる若い人が多くなって、なんだかちょっと気持ち悪いよね。プレゼンが上手だとか、そういう人ばかりが評価される時代になっているけど、プレゼンが上手でも、内容が薄っぺらい人だっている。もっと自由な発想で、他人からどう思われるかは気にせず、自分はこういう人間なんです、と言える方が大事だと思います。
もっとロックに!
僕は、思春期にロックを聴いていたことが大きかった。ロックって、途中でテープが逆回転したり、いきなり曲調が変わったり、とにかく“なんでもあり”なんですよ(笑) ロックには、どんなことをやっても世界としては成立している“存在の自由さ”を、とことん叩き込まれた気がします。今はいろんな情報で溢れているから難しいかもしれないけど、若い人には周囲の評価とかさまざまな束縛から解き放たれて、もっと自由に、ロックになってもらいたいですね。
会社員人生終えたとき、どんな顔をしているか
僕が会社で働いていた頃にお世話になった方々がリタイアされるとき、幸せそうに辞めていく人は、自分のやりがいや強みを見つけてやり遂げた人です。偉くなったかどうかは関係ないですね。好きなことを極めている限り、その会社員人生は失敗ではないと思うんです。自分がこういう人間だから、こういうことをやり遂げたい。出世とかポジショニングより、それを見つけた人の方が60歳、65歳になったときに良い会社員人生だったと思えますよ。
磯﨑さんのご愛用のアイテムを教えていただきました。

1「ビルケンシュトック」のサンダル
「365日中、300日はビルケンシュトック」というほどの愛好家。一度履いたら病みつきになる楽な履き心地が魅力。

2「LIFE」のノート
書き心地や使いやすさにこだわったノートや手帳を作り続ける日本の老舗ブランド LIFE(ライフ)。「読み返すことは滅多にないけど、備忘録として書いておくと不思議と忘れない」

磯﨑 憲一郎
Kenichiro Isozaki
小説家
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授
1965年 千葉県生まれ
2007年 「肝心の子供」で第44回文藝賞を受賞
2009年 「終の住処」で第141回芥川賞を受賞
2011年 「赤の他人の瓜二つ」で第21回東急文化村ドゥマゴ文学賞を受賞
2013年 「往古来今」で第41回泉鏡花文学賞を受賞を受賞
他の著作に「眼と太陽」「世紀の発見」「電車道」「鳥獣戯画」、横尾忠則氏・保坂和志氏との共著「アトリエ会議」等がある。1988年から2015年まで三井物産株式会社勤務。現在、朝日新聞「文芸時評」執筆者、文藝賞選考委員。
取材後記
お話のなかで、「何でもあり」という言葉が印象的でした。キャリアを形成する過程では他者の評価が付き物です。自分がどう思われているかを気にするあまり、評価される能力へ力を注ぐこともあるのではないでしょうか。しかし、自己を顧みることが結果的に個性を磨くことに繋がるのではないかと思いました。制度や環境ではなく、自己の意識から働き方を自由にできる可能性を感じさせるお話でした。
RECOMMEND
あわせて読みたいおススメの記事






RANKING
ランキング




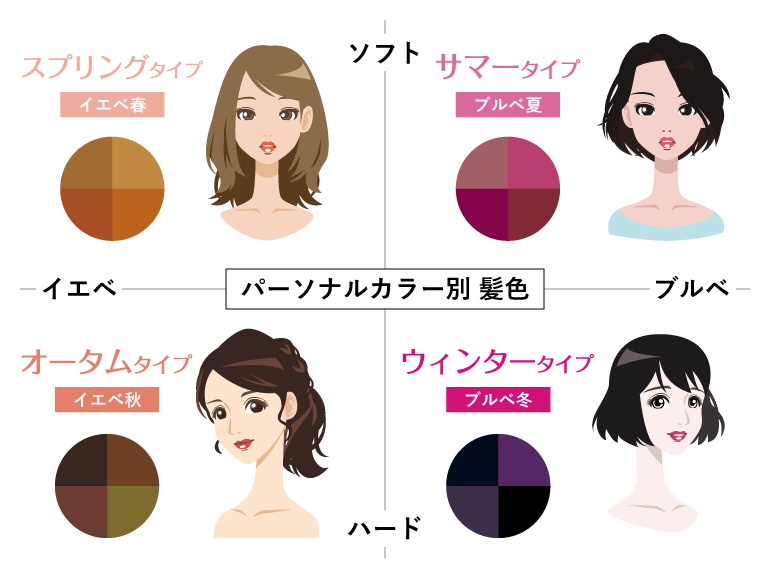
作家の磯﨑憲一郎氏は、総合商社三井物産勤務時に新人作家の登竜門といわれる『文藝賞』を受賞し、作家デビューを果たした異例の経歴の持ち主。三井物産退社後、現在は東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の教授を務める一方、朝日新聞『文芸時評』で執筆、文藝賞選考委員としてもご活躍されている。
今回、特別にお話を伺うことができ、会社員から作家になったきっかけや当時の心境などを取材した。また、三井物産勤務時代に人材開発室長として採用面接に従事していたご経験から、今の学生の就職活動で感じたことも伺った。